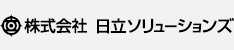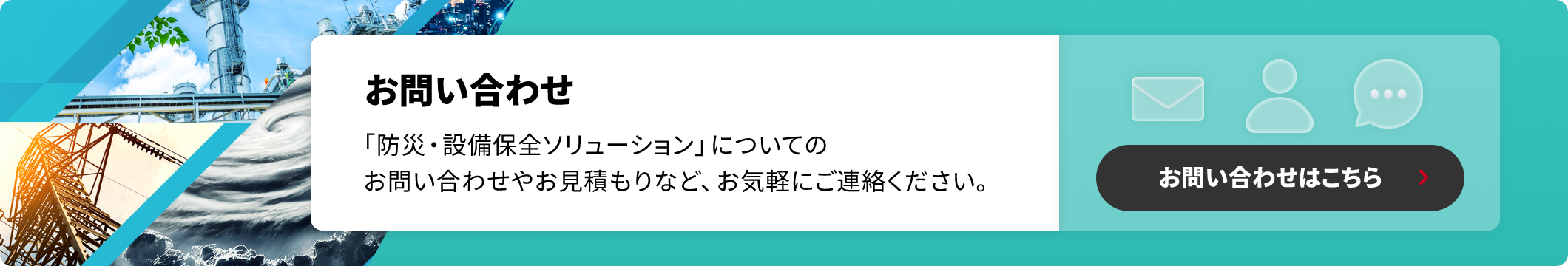災害対策について
近年増加する気象災害
近年、世界レベルで気候変動による豪雨災害などの気象災害が増加しています。洪水や土砂災害を引き起こす大雨や短時間強雨の回数は増加傾向にあり、土砂災害の発生回数も比例して増加しています。気候変動に関する状況を考えると、この傾向はしばらく続いていくことになると思われます。※グラフ1参照
自然災害の増加による影響は企業にも及んでおり、多額の企業損失が出ている事例もあります。地震だけでなく、台風などの豪雨による被害も大きなものとなってきています。※グラフ2参照
災害発生時における企業の持続可能性を高めるためには、企業自身でBCP策定などの対策を実施することが重要と考えられています。
グラフ1:日降水量200mm以上の年間日数および1時間降水量50mm以上の年間発生回数の推移

出典:気象庁Webサイトをもとに作成
グラフ2:火災保険の自然災害による支払保険金

出典:一般社団法人 日本損害保険協会Webサイトをもとに作成
企業における災害対策について

企業における災害対策において、従業員の安全確認(確保)はもちろんのこと、ビジネスの継続性の確保が重要です。
災害対策を検討するには、平常時(発災前)、発災時、復旧時の3つのフェーズに分けて検討していく必要があります。各フェーズを更に細かく分ける考え方もありますが、ここではわかり易く3つのフェーズで解説します。
-
平常フェーズ(発災前)
企業の災害リスクを評価・分析して防災計画・事業継続計画(BCP)を策定し、災害時の対応手順(重要業務の優先順位付けや代替手段の検討)を明確にします。また、従業員への定期的な防災訓練や設備・備品の定期点検も必要です。
-
発災フェーズ
災害時には、迅速かつ適切な対応が求められます。まずは従業員の安全を確認し、気象情報や被害情報、交通情報などを収集、関係者へ情報を共有することで被害の拡大・二次災害を防ぎます。事前に策定した初動対応計画に基づき、事業継続や早期復旧をめざします。
-
復旧フェーズ
被害状況を確認し、復旧作業を実施しながら段階的に事業を再開します。代替手段やリソースを活用して、事業の早期復旧を図ります。復旧後は、災害対応の結果を検証し、改善策を検討します。改善策を防災計画に反映することで、将来的なリスクを低減することができます。
災害対策を3つのフェーズに分けて、検討・計画・実施することで、企業の持続可能性を強化することができます。
ICTを活用した気象災害対策
災害対策の一環として、ICTの活用があります。
気象情報や地図情報、設備情報など、企業内で蓄積される情報と外部のさまざまな情報(地理情報や気象情報など)を組み合わせて活用することで、発災時の情報収集や状況把握、初動対応などを支援することができます。例えば、気象災害は地震のように予兆が難しい災害とは異なり、気象現象を蓄積・予測することで、災害対策を講じ易いとされています。事前に、ICTを活用した対策を準備することで、企業へのダメージを局所化・最小化することにつながります。
気象情報とICTを活用した災害対策
-
平常フェーズ(発災前)
気象情報の配信業者からリアルタイムの情報を入手することで、災害の予兆を把握し、発災に備えることができます。
また、地理情報を活用することで発災時の地理的なリスクを可視化し、対策を検討することができます。 -
発災フェーズ
気象情報や災害情報の収集において、ICTは強力なツールとなります。気象情報の配信業者から提供される情報、企業が独自に設置したセンサーや現場作業員のモバイル端末を介して得られる独自情報を活用すれば、よりリアルな被害状況を可視化することができます。
スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末、メールやSNSなどコミュニケーションツールは、初動対応における連絡ツールとして大きな役割を担うことができます。 -
復旧フェーズ
初動対応に続き、モバイル端末や各種コミュニケーションツールを活用することで、復旧活動時の被害情報・復旧情報の共有、巡視・点検作業の支援が可能となります。
復旧後は、ダッシュボードや解析システムを用いた報告書作成や活動履歴を蓄積して次の災害時に活用する…といった支援を可能とします。
ICTを導入する際は、通常の業務でも活用可能なシステム(もしくは通常の業務に関連するシステム)を選定することを推奨します。災害対策にのみ特化したシステムを導入する場合、企業によってはコストメリットの観点で導入障壁が高くなる場合があります。通常業務においても活用・関連するシステムであれば、導入障壁を下げることができるでしょう。
ICTの選定ポイント
-
正確で迅速な災害情報の収集が可能であること
信頼できる企業と連携し、スピーディーで正確な気象情報や災害情報を収集できる仕組みを整える必要があります。
-
多くの関係者において情報共有(連携)が可能であること
さまざまな情報を収集しても、関係者にその情報が共有されなければ意味がありません。災害時にも情報共有ができるような仕組み作りが重要です。
-
災害時にも安定稼働すること
災害時にはITインフラの物理的な破損だけでなくサーバーに負荷が集中するため、信頼性の高いシステム構築経験のあるベンダーかどうかの見極めが必要です。
-
二次災害の抑制
情報収集においては現場の作業員が大きな力を発揮しますが、災害時には作業員の安全を守る仕組みが必要です。
-
情報を蓄積し、次の災害時に再利用できること
将来発生するかもしれない災害のために、実際に経験した災害情報や初動対応情報、復旧作業情報などのデータをナレッジとして蓄積する仕組みも必要です。
災害対策は、一度策定しただけでは終わらず、継続的な見直しが必要です。
企業の方針や技術の変化に合わせて最新のICTを活用し、企業の持続可能性を高めていきましょう。

製品・サービス一覧

GeoMation 災害対策ソリューション
多発する自然災害のBCP対応をトータルサポート。
地震および気象災害(台風、大雨、洪水、土砂災害)の対策業務を効率化し、平常時・発災時・復旧時まで一貫して支援。
詳細をみる防災・設備保全ソリューション コンテンツ一覧
関連商品・キーワード
本サイトの会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。