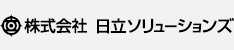リードナーチャリングとは
リードナーチャリングとは、見込み客(リード)を育成(ナーチャリング)することです。リードに対してメールやSNSなどを使って継続的かつ段階的にアプローチを行うことで、購買意欲を高めていきます。
リードジェネレーションとの違い
リードジェネレーションとは、リードを獲得するための活動を意味します。したがって、リードジェネレーションの次の段階にリードナーチャリングが位置付けられます。リード情報の獲得は、セミナーや商品展示会、アンケート、資料請求、メールの開封・クリックなどの機会を通して行います。
リードジェネレーションについては以下の記事で詳しく解説しています。
>リードジェネレーションとは?意味や手法、ナーチャリングとの違いについても解説
リードクオリフィケーション
リードクオリフィケーションとは、リードナーチャリング中のリードを選別することです。すでに獲得・育成中のリードについて、説明会への参加やメール開封率、クリック率などの行動から、購買意欲が高いとみられるリードを選別します。
リードクオリフィケーションでは、リードの行動から得られる購買意欲度を数値化するリードスコアリングが役に立ちます。
リードスコアリングについては以下の記事で詳しく解説しています。
リードナーチャリングが注目される背景
リードナーチャリングが注目される背景には、次のような顧客や購買行動の変化があります。
インターネットの普及にともなう購買プロセスの変化
インターネットを介して顧客自身が商品やサービスの情報を集められるようになったことで、以前のように営業の訪問や提案を受けてから検討を始めるのではなく、営業が介在しないうちに商品やサービスの選定が終わっていることも多くなりました。
一方、B2Bの購買プロセスにおいては、インターネット上で検索し比較検討するステップが増えたことにより、以前と比較して購買プロセスの長期化・複雑化の傾向があります。
オンライン+オフラインによる顧客接点の増加
対面のオフライン営業活動に加えてオンラインでのやりとりが増えたことから、顧客接点(タッチポイント)の総数は増加しています。そのため、以前よりも増加したリードに対してアプローチしきれず、多くが休眠顧客となってしまう問題も発生しています。
こうした購買プロセスの変化やリードおよび休眠顧客の増加に対して、取りこぼしの多い古い営業スタイルに変わり幅広いリードを対象に効果的なアプローチが期待できる「リードナーチャリング」に目を向ける企業が増えています。
リードナーチャリングの手法
では、リードナーチャリングにはどのような手法やツールが活用できるのでしょうか。
SNS
X、Facebook、YouTube、LINEなどのSNSを活用して自社の商品・サービスの認知度向上やブランディングを行うことは、今や欠かせない手法となっています。フォロワーの獲得で顧客接点を増やせるだけではなく、情報を容易に拡散でき、顧客とのカジュアルなコミュニケーションが直接取れるところに、リードナーチャリングにおいてSNSを活用するメリットがあります。
インサイドセールス
インサイドセールスとは、リードに対して非対面で営業を行う手法です。メールや電話、SNS、Web会議システムなどを活用してリードナーチャリングを行います。さらにリードを精査し、商談に結びつく確度の高いリードについては対面営業(フィールドセールス)に渡します。
このように、非対面と対面のアプローチを効果的に組み合わせる営業手法とリードナーチャリングとは、相互補完的な関係があります。
メール
メールナーチャリングとも呼ばれるように、メールによるリードナーチャリングは多くの企業で採用されている手法です。業務時間内にメールをチェックする機会が多いことから、B2Bのナーチャリングとして有効なツールだといえます。
メールによるリードナーチャリングには、主に次の3つの種類があります。
- メルマガ(メールマガジン):リードに対して定期的に一斉配信するメール
- セグメントメール:リードを条件でセグメント化し、特定のコンテンツを配信するメール
- ステップメール:リードの確度や条件に合わせて、段階的に配信するメール
セミナー開催
自社の製品やサービスを説明するセミナー開催も広く採用されているリードナーチャリングの手法です。
セミナー開催については、会場での対面セミナーとオンラインセミナーの2種類があります。
会場での対面セミナーは直接顧客とコミュニケーションができるメリットがあります。ただし、時間と場所に制約があるため、参加できるリードが限定されるデメリットがあります。一方、オンラインセミナー(ウェビナー)は時間や場所の自由度が高く、より多くのリードを集めることができます。その一方で、顧客との密なコミュニケーションがしにくい面もあるため、チャットなどをうまく活用して双方向コミュニケーションを心がける必要があります。
リターゲティング広告
リターゲティング広告とは、一度訪れたサイトやクリックした製品、サービスがほかのサイトの閲覧中にも広告として表示される仕組みのことです。自社の商品やサービスに興味を持ったリードに対し広告を表示することで思い出し買いを促したり、購買意欲を高めたりすることが期待できます。
ツールの活用
マーケティングオートメーション(MA)とは、リード情報を一元管理しリードの獲得から商談成立までのプロセスを効率化するツールです。MAツールを活用すれば、大量のリードから特定の条件で対象を抽出して一斉メールを配信するなど、リードナーチャリングを効率よく実施することができます。
リードナーチャリングのメリット
リードナーチャリングでは多くのメリットが期待できますが、大きくは次の2つに集約できます。
見込顧客の離脱を防ぐ
営業活動は購買意欲の高いリードに対して優先的に行われるため、リードナーチャリングが行われない場合、購買意欲が低いリードについてはどうしても放置されがちです。その結果、顧客は競合他社の製品やサービスに流れてしまうかもしれません。
リードナーチャリングでは、確度の高くないリードに対しても自社の製品やサービスへの購買意欲を高めていくようにナーチャリングを行なっていきます。それによりリードの離脱を防ぐ効果が期待できます。
業務効率が向上する
リードナーチャリングを行うことで、リードクオリフィケーションの精度を高め、確度の高いリードを営業部門に渡すことができます。営業部門では確度の高いリードに対して優先的に営業活動を行えるため、受注率・成約率を高めることにつながります。
リードナーチャリングによってマーケティング部門・営業部門の間での効果的な分業と連携が可能となり、営業活動全体の効率化も促進できます。
リードナーチャリングのデメリット
リードナーチャリングから十分なメリットを享受するために、考慮しなければならないことも押さえておきましょう。
リードナーチャリングの効果を得るまでには、ある程度の時間がかかります。また、リード数が少なすぎるとリードナーチャリングで効果を得ることが難しくなります。リード数が少ない段階であれば、まずリードジェネレーションに注力するのも一つの方法です。
さらに、大量かつ多様なデータを扱うことから、効率化のためにはツールの活用が欠かせません。
このように、リードナーチャリングには一定の時間とコストがかかる点を考慮しておく必要があるでしょう。
リードナーチャリングの流れ

それでは、リードナーチャリングの基本的な流れを確認しましょう。
情報を一元管理する
リードの獲得ソースはさまざまですが、個別にリードナーチャリングを行うのではなく、すべてのリードを一元的に管理したうえでリードナーチャリングを行います。リード数を大きくすることによりリードナーチャリングの効果も高めることができます。
リードをセグメント分けする
リードを一元化したら、次はセグメント分けを行います。どのセミナーで獲得したのか、何の資料をダウンロードしたのかなどのリード獲得ソースの種類や、性別・年代・地域などのリードの属性、購買意欲の度合いなどによってリードを分けていきます。
カスタマージャーニーを描く
セグメント分けしたリードについて、さらに購買プロセスを時系列で細分化し、何を求めているかを明らかにしていきます。各フェーズのリードの行動を把握するには、AIDMAやAISASなどの購買プロセスフレームワークが活用できます。
さらに、カスタマージャーニーマップを作成して各フェーズのタッチポイント(顧客接点)における施策を立てていきます。カスタマージャーニーマップではリードのペルソナを設定し、製品・サービスの認知から購入までの間にどのような思考・感情・行動をとるかを可視化していきます。これにより、リードを深く理解し、自社の施策について意思決定の裏付けをすることができます。
リードナーチャリングのゴールを設定する
リードナーチャリングは繰り返し実施するため、どの状態になったら営業にリードを渡すのかについてゴールを決めておく必要があります。ゴールを設定しておくことは、リードナーチャリングの効果を検証するうえでも役に立ちます。
リードの属性に合わせたコンテンツを作成する
セグメントやフェーズごとのリードに対する理解を深めたら、リードに提供するコンテンツを作成します。ここでは、カスタマージャーニーを描いた際にタッチポイントで検討した内容を参考にするなど、リードが関心を持ちそうなコンテンツを考えます。
リードナーチャリングのポイント
効果的にリードナーチャリングを行うためには、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
目標設定を行う
リードをマーケティング部門から営業部門へ渡すタイミングを明確にして効果検証を可能とするために、リードナーチャリングのゴールを設定しておきます。
例えば、リードの状態をホット/ウォーム/コールドの3つに分け、「半年間でウォームリードのうち20%をホットリードにする」といったような定量的なゴール設定をするとよいでしょう。
- ホットリード:「すぐ買いたい」と購買意欲が最も高い状態。リード情報も整っている。
- ウォームリード:購買意欲がありそうな多くのリードの状態。リード情報は収集中。
- コールドリード:関心が薄く、購買意欲はほとんど育っていない状態。
確度の高いリードの定義を決める
確度の高いリード=ホットリードは購買意欲が最も高いリードの状態ですが、その定義を具体的かつ定量的に決めておくことが重要です。以下のような項目に点数を設定し合計値を出すスコアリングが役に立ちます。
- メール開封
- メールクリック
- Webページ閲覧
- 資料ダウンロード
- セミナー参加
- 見積もり請求 など
さらに、購買プロセスにおけるポジション(意思決定者かどうか)やアンケートの結果(購入予定の有無)によってもスコアリングすることができます。
部門間での情報の連携をおこなう
マーケティング部門でリードナーチャリングを行い、確度の高いリードを営業部門に渡す、といった分業体制で取り組みます。営業にリードを渡した後も、リードが成約にまで至ったのかどうかによってリードナーチャリングの効果を検証し、リードナーチャリングの段階でどのような情報を収集しておくべきかのフィードバックを受けるなど、部門間の連携が重要となってきます。
リードナーチャリングはSalesforce
Salesforce では、リード情報の一元管理と部門間での連携、獲得したリードの行動に合わせたコンテンツの配信などが可能です。これにより、タイミングを逃すことなく、よりパーソナライズされたマーケティング活動を行うことができます。
Salesforce の Account Engagement(旧Pardot)では、Webサイト訪問者の行動のトラッキングやスコアリングによってリードを発掘することができます。また、リードジェネレーションに必要なコンテンツの作成を支援するツールやリードナーチャリングの自動化により、営業部門へ渡すリードの質を効率的・効果的に向上させることができます。

お気軽にご相談ください
「費用はどれくらい?」「導入スケジュールは?」
「他社の事例を教えてほしい」「製品の仕様は?」など、お気軽にご相談ください。

「オンデマンドCRMソリューション Salesforce」の資料をダウンロードいただけます。

SFA・CRM・MAに関するさまざまなテーマについて日立ソリューションズの知見をもとに有益な情報を発信していきます。
記事のまとめ
リードナーチャリングは、獲得したリードをセグメント分けし興味・関心のあるコンテンツを提供することで購買意欲を効率的に高めていくマーケティング手法です。
SNSやウェビナーなどのデジタルツールに加え、リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーションに有効なツールも活用してマーケティングと営業活動の質を全社的に高め、効率化をめざしましょう。