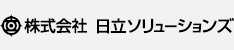スマートマニファクチャリングソリューション
IoTプロジェクトの実践、つながる工場をめざすユースケースより
連載『“失敗しない、止まらない”IoTプロジェクトの処方箋』#04

はじめに
前回は、『日本流のオープンクローズ戦略』でIoTに取り組むというお話をしましたが、概念的なものが中心でしたので「今ひとつイメージがつかめない」と思われた方が多かったのではないかと思います。今回でこのコラムは最終回となりますので、筆者が取り組んできたIoTプロジェクトを参考にしながら、できるだけわかりやすく事例などをあげてケーススタディ風に取り組みをご紹介したいと思います。
製造業のIoTプロジェクトでめざすのはバイモーダルのビジネス
IoTに、社内向けとか社外向けと言う区別はありません。つまり、1つの技術を実用化すれば社内利用もお客さま向けにも使えるはずです。IoTという技術に決まったルールやなどありませんから、前例や慣例などにこだわらず使えるものはどこにでも使えばよいと思います。これからの製造業は” よい製品(モノ)を作って売る”だけではなく、” よい製品(モノ)と、モノから得られる情報(データ)をサービス(コト)を提供する”ことができます。
モノだけ買うお客さま、サービスだけ欲しいお客さま、モノとサービス両方が必要なお客さまそれぞれ大切になります。他社の製品(モノ)を使っているお客さまへ、よいサービスを提供できれば、次の機会に自社の製品(モノ)を買っていただけるでしょう。IoTで得た情報を利用して、これまで以上によい製品(モノ)を早く安く生産できるようになるでしょう。IoTは、こうしたサービスを提供するために必要な情報(データ)を入手する技術です。製造現場で、設備の稼働状況を監視したり原材料/部品の所在と数量を把握したりする手段としても使えます。前者のサービスは、社外のお客さま向けに提供するシステム:SoE(システム・オブ・エンゲージメント)と言います。後者のサービスは、社内の現場担当者向けに提供するシステム:SoR(システム・オブ・レコード)と言います。最近では、SoEを”モード1”、SoRを”モード2”と呼ぶことがあり、1つの技術を2つのモード(お客さま向けモードと社内担当者向けモード)に使い分けることから、「バイモーダル」と言う使い方をするようです。
(参考:バイモーダルITとは何か? 企業がITの「2つの流儀」を使い分ける方法 https://www.sbbit.jp/article/cont1/34971)
筆者は、インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ(IVI)という組織のメンバーとして製造業におけるIoTに取り組んでいます。未来の製造業のイメージは、製品(モノ)がネットにつながって、ここから多様な情報(データ)が得られるようになる。入手した情報(データ)を社内で上手く活用すれば、よりよい製品を早く安く作れるようになる。入手した情報(データ)をお客さま向け活用すれば、サービス(コト)を提供できれば顧客満足度の向上やサービスビジネスが実現できる。つまり、データを上手く使いこなした企業が勝ち残ると言われています。データの使い方には、3つのステップがあります。以下の3つのステップを実現して、製品(モノ)とサービス(コト)が互いに補完し合って価値を高めていくことができます。
STEP1. データを集めてモノの動きを可視化する(見える化「監視」)
STEP2. 集めたデータを使って生産性を高める(省力化とコストダウン「保守運用」)
STEP3. ネットで遠隔地からモノを操作する(自動化やリモートコントロール「制御」)
在庫圧縮率約30%!
【詳細資料】在庫管理状況(欠品、品薄、過剰など)の自動抽出/可視化による保守部品の在庫最適化資料ダウンロード
欠品・品切れなどの種別ごとに在庫状況を可視化して、問題の早期発見と迅速な対策を実現の資料はこちらからダウンロードできますので是非ご覧ください。

おすすめコンテンツ
日本の製造業が取り組むべき“スマートマニュファクチャリング”の実現について具体的な事例や取組みなどを交えて具体的な取り組みへのアプローチについてご説明します。
データ利活用の現状と「当たり前」による劇的な改善についてご説明します。