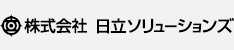スマートマニファクチャリングソリューション
データ分野における水道哲学と変革管理の実現
連載『データ流通時代の日本の商機』#02

データ利活用の現場において、なぜ「あたりまえ」ができていないのか。その原因は、経営者に意欲や能力がないという話ではなく、ビジネスモデルに大きく関係しています。それではその「あたりまえ」の実現を阻んでいるものは何か。次にこれを考えてみたいと思います。データ利活用によって業務改善を行うユーザー企業側と、そのデータ利活用のサービスを提供するITベンダー企業側と、それぞれの課題を述べたいと思います。
変革管理(Change Management)
最初に、データ利活用の現場、ユーザー企業側を考えてみたいと思います。データの利活用では、現実世界からデータを取り出し、取出したデータを蓄積し解析し、それを現実世界へ適用するというサイクルがあります。我が国では、データ利活用というと、情報技術に着目して、データの収集・蓄積・解析には積極的取り組みがちです。大きな課題は、最後の現実世界への適用で、ここがうまくいきません。特に、経営・ビジネスを変えていくこのプロセスに関して、経営者の意識・経験・情緒的なものを重視するあまり、ある意味で軽視されているように思います。
他方、米国ではデータを経営に結びつけるための組織変革を非常に重視してり、変革管理(Change Management)が重要な研究対象です。例えば、データの利活用によって業務プロセスを改善すれば、必ず仕事の現場は変わり、最も極端には、特定の職種は不要にすらなります。個々の現場の人には、こうした変化には反対・反感が起こり受け入れられず、そこで頓挫します。仕事の変化を受け入れてもらうための心理学的手法は、変革管理が扱う重要な分野です。それだけでなく、組織も変えなければいけませんし、その業務を支援するITシステムの更新も必要です。こうしたことが、スムーズに進んで、はじめてデータ利活用による経営改善・業務改革が実現されます。
データ利活用分野における水道哲学
一方、「あたりまえ」が多く残存していると、データ利活用サービスを提供するITベンダーは一体何をやっているのか、とも言いたくなります。どうも「あたりまえ」が進まないところをみてまわると、ユーザー側の現場とベンダー側の間での損益分岐点が異なっています。要は、まだデータ利活用ソリューションが高すぎるのです。ベンダー側のコスト構造もわかるのですが、そのままでは多くの「あたりまえ」はそのまま残存してしまいます。ベンダーであるIT企業が、全国で広く薄く収益化し、大きく積みあげることが必要だと思います。
松下電器の故松下幸之助氏の経営哲学の一つに「水道哲学」があります。企業の使命は、高品質の製品を広くあまねく、水道のように日本全体、隅々までの送り届けることだとおっしゃっています。データ利活用分野の対象は、ハードウェアである家電製品ではなく、サービスだという部分は違いますが、シリコンバレー的な一攫千金型ビジネスモデルではなく、水道哲学的なビジネスモデルの確立が求められていると思います。それは国内だけでなく、世界に通じる、まだ誰も確立していない方法だと思います。これから我が国におけるイノベーションを期待したいと思います。
具体的なユースケース付き
【詳細資料】スマートマニュファクチャリング
カタログ詳細資料ダウンロード
進化し続けるIoTやAI、ビッグデータといったデジタル技術を活用し、工場の製造データ連携や生産技能伝承さらにはアフターサービスの付加価値向上など製造業のパフォーマンス向上をめざす取り組み「スマートマニュファクチャリング」が注目されています。
この資料では具体的なユースケースを交え、日立ソリューションズがご提案するスマートマニュファクチャリングソリューションの詳細を紹介します。
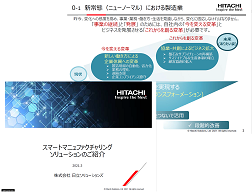
おすすめコンテンツ
なぜほとんどのIoTプロジェクトは途中で止まってしまうのかについて事例をもとに説明します。
データ利活用の現状と「当たり前」による劇的な改善についてご説明します。