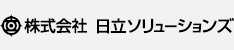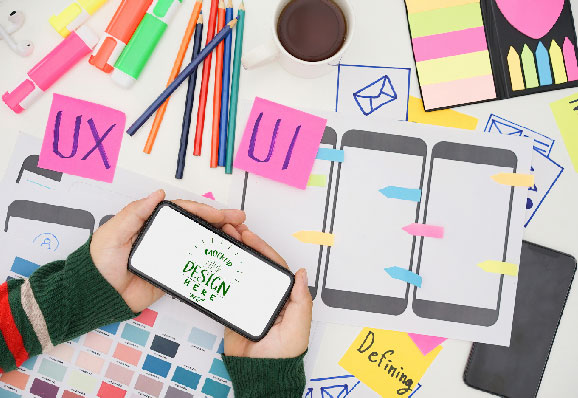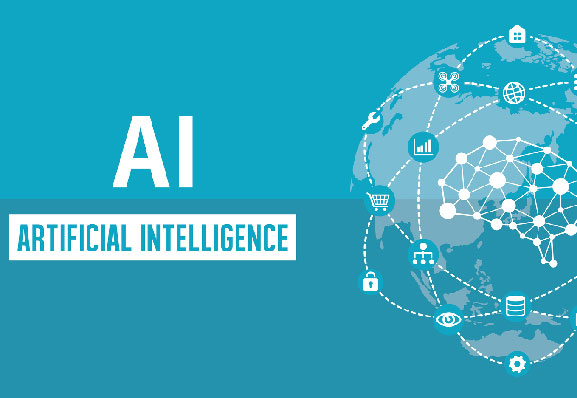デジタルマーケティングソリューション
電子決済とポイントサービスの利用調査

日本でも徐々に浸透が進む電子決済(キャッシュレス決済)、およびそれに付随して集客やマーケティングにも効果を発揮するポイントプログラムですが、消費者としてのユーザーは電子決済やポイントプログラムに何を求めているのでしょうか。ここではマイナビニュース会員200人(20〜60代の会社員)を対象としたアンケートの結果から、ユーザーが何を求めているかを浮き彫りにしていきます。
目次
資料ダウンロード

PointInfinity
マルチ決済ゲートウェイ
複数のQRコード決済(マルチ決済)と複数の共通ポイント(マルチポイント)をまとめて導入できるゲートウェイサービスです。
9割近くが電子決済を利用
前回までに見たように、日本において電子決済の普及は今後の大きな課題だといわれていますが、実感として、とりわけ若い世代では「すでに電子決済をけっこう使っている」という人も多いのではないでしょうか。 まずは、買い物の際に電子決済サービスを利用するかどうかについて質問しました。結果は、「よく利用する」が55.0%、「ときどき利用する」が31.0%となり、実に9割近くが利用している実情が浮かび上がりました。50〜60代でも「よく利用する」「ときどき利用する」と答えた人が多く見られます。

今回は調査対象の職業が会社員であり、他の職業や地域差などで結果が異なることも考えられますし、70代以上で現役をリタイヤした高年齢層はスマートフォンに慣れていないこともあってまだまだ浸透していない可能性もたしかに考えられます。しかしながら、欧米各国や中国、韓国などのアジア諸国と比べて電子決済が進んでいないといわれる日本でも、急速に浸透している現状が見て取れるでしょう。
利用者はどのサービスを使っている?
利用した電子決済サービスの実情(複数回答可)を見ると、日本で古くから定着しているクレジットカードが9割近く、Suicaなどの電子マネーが8割を超えており、いわゆるカードタイプのものが主流を占めています。50〜60代でもスマートフォン決済を利用している人はいますが、やはり年齢層が高くなるとクレジットカードのみ、あるいはクレジットカードと電子マネーという答えが多くなる傾向が見られます。

クレジットカードは、これまで一般的に数千円以上の比較的高価な買い物でよく使われていたようですが、最近はスーパーマーケットなどサインレスで使えるところも多くなっているので、ちょっとした買い物で使用するケースも増えているかもしれません。また、Suicaなどの交通系電子マネーは年齢層を問わず電車やバスに乗るときに使われているので、電子決済であることを意識せずに利用しているケースも多いことでしょう。
一方、QRコード・バーコードを使ったスマートフォンによる決済についてはどうでしょうか。これも同設問で利用するという回答が5割を超えており、昨今のスマートフォンとスマートフォンアプリを使った決済手段の普及が進んでいる現状も見て取れます。
気になる点としては、「スマホ決済(QRコード・バーコード)について、今後どれくらいの頻度で利用していきたいと考えていますか」という設問への答えです。今後も利用したいと答えた人が「積極的に利用したい」「場合によっては利用したい」を合わせて8割近くに達しているにもかかわらず、内訳はほぼ半々で、何らかの事情がなければ積極的には使わないという声が表れているようにも見えます。

利用の契機として重要なポイントサービス
そこで注目したいのが、ポイントサービスとの関連でしょう。「電子決済サービスを選ぶ際、ポイントサービスを意識しますか」との問いに対し、「とても意識する」と答えた人は66.0%にも上っています。「ポイントサービスでは何を重視しますか」と複数回答で尋ねた結果としては「ポイントの還元率」が8割を超えており、購入時にポイントの還元が多ければ、つまり“お得”であれば電子決済を利用するという現実的な声が多いのが実情といえそうです(ちなみに2位は「加盟店の幅広さ」で、5割強)。

背景としては、2018年来、QRコード・バーコードの決済アプリが大規模なポイント還元キャンペーンを立て続けに打った影響が考えられます。加盟店で10万円クラスの高価な買い物をした場合に全額還元となるケースもあったことから、ニュースでも大々的に報じられ、世代を問わず注目を浴びました。現在でも、上限額は低く設定されていますが「20%還元」などのキャンペーンが頻繁に開催されており、そうしたポイントサービスの有無がユーザーをつなぎとめている部分は無視できないでしょう。
クレジットカードや交通系・流通系電子マネーのように、カードを取り出すだけで決済できる手段と比べ、スマートフォンのQRコード・バーコード決済はアプリを起動するというワンクッションの動作が必要になります。QRコード・バーコード決済を今後も増やしていくには、ポイントサービスの訴求が重要であることに加え、さらに容易に利用できるシステム上の工夫も大きな意味を持ちそうです。
クレジットカードは主役であり続ける?

今回のアンケート結果からも見えてくるように、現状、電子決済、とりわけスマートフォンのQRコード・バーコード決済については、お得なポイントサービスの存在が大きな契機になっているようです。一方、少額利用も増えてきたクレジットカードや、毎日通勤通学で欠かさず使用する交通系電子マネーについては、とくにお得なポイントサービスを前提とすることなく、今後も一定水準を保って推移するか、あるいはさらなる増加が期待できそうです。
一般社団法人キャッシュレス推進協議会が2019年4月に発表した「キャッシュレス ロードマップ 2019」に掲載された資料によると、キャッシュレス支払額の約9割をクレジットカードが占め、今後も順調に伸びていくと予測されています。クレジットカードは決済端末が高価であることや、売上から入金までのサイクルが長いといった理由で、全国には未加盟店がまだまだ残っています。しかしキャッシュレス決済推進の流れに乗って、導入しやすい安価な端末を提供したり、最短翌日といった短い入金サイクルをアピールするカード事業者も出てきているので、キャッシュレスの主役としてまだまだ伸びていくことでしょう。
クレジットカードにも各社独自のポイントサービスがあり、最近は他業態とのポイント相互乗り入れも盛んになっているので、スマートフォン決済のようにポイントサービスの重要性が一段と高まっていくかもしれません。
まとめ
日本は“現金信仰”が強い国といわれ、とりわけスマートフォン決済では、お得なイメージを与えるポイントサービスないと「現金で払ってしまおう」と考える層は今後も一定程度残りそうです。しかし一方で、政府がキャッシュレス推進政策に力を入れ、民間企業もさまざまなサービスを打ち出して電子決済の浸透を進めようとしているので、普及の流れは一段と加速していくでしょうし、お得なポイントサービスの存在が電子決済利用のモチベーションを刺激し続けることも間違いないと考えられます。
電子決済が進めば、そこで得られるビッグデータが飛躍的に増加し、そのデータをマーケティングに活用できるチャンスも確実に広がっていきます。電子決済の進む先を今後も注視したいところです。
電子決済関連ソリューション
ポイント管理
関連する調査レポート
関連コラム
- デジタルマーケティングとは?今さら聞けないマーケティング基礎知識・資格・導入メリット
- デジタルマーケティング戦略の立案方法【基本編】
- 【入門】AI(人工知能)・機械学習とは?その種類とマーケティング手法・成功事例
- AI・機械学習で変わるマーケティングとは?
- オムニチャネルとは?マルチチャネルとの違いとオムニチャネル戦略成功のポイント
- 他社成功事例から学ぶオムニチャネルマーケティング
- 顧客との関係性を向上させるCRMツールの選定ポイント
- 会員管理システム(CRM)とは?導入して売り上げにつなげる手法を徹底解説
- CMSとは?初心者でもわかるCMSの種類、メリット、導入事例【おすすめは?】
- CMS選定で失敗しない!CMSを選ぶポイント
おすすめコンテンツ
日立ソリューションズが考えるデジタルマーケティングについてご紹介します。
デジタルマーケティングに関するトレンド、ノウハウなどを研究成果としてお届けします。
ホワイトペーパー ダウンロード

スマホ決済のさらなる普及が期待できる結果に!期待する効果第1位は... 「店舗におけるキャッシュレス(スマホ)決済に関する調査レポート」
お役立ち資料DL
店舗におけるキャッシュレス(スマホ)決済に関する調査レポート

閲覧が多い記事
Tagで絞り込む