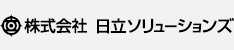- TOP
- コンセプト
-
製品・サービス
製品・サービス
自由な働き方 Smart Workplace
6Connex Virtual Event Platform 遠隔プレゼンテーション Personify Presenter バーチャル背景設定ツール ChromaCam 仮想デスクトップ導入ソリューション 活文 Managed Information Exchange(Outlook連携・Zoom連携) 電子契約ソリューション(DocuSign) 電子印鑑GMOサイン ワークマネジメントソリューション for monday.com 秘文 Endpoint Protection Service Microsoft 365 導入ソリューション テレワーク向けセキュリティ点検ソリューション グループタスク リマインダーサービス Miroハイパーオートメーション Hyper Automation
働きがい Employee Experience
働き方改革ソリューション
- 導入事例
- 動画
- コラム
- セミナー
- キャンペーン情報
- TOP
- コンセプト
-
製品・サービス
製品・サービス
自由な働き方 Smart Workplace
6Connex Virtual Event Platform 遠隔プレゼンテーション Personify Presenter バーチャル背景設定ツール ChromaCam 仮想デスクトップ導入ソリューション 活文 Managed Information Exchange(Outlook連携・Zoom連携) 電子契約ソリューション(DocuSign) 電子印鑑GMOサイン ワークマネジメントソリューション for monday.com 秘文 Endpoint Protection Service Microsoft 365 導入ソリューション テレワーク向けセキュリティ点検ソリューション グループタスク リマインダーサービス Miroハイパーオートメーション Hyper Automation
働きがい Employee Experience
働き方改革ソリューション
- 導入事例
- 動画
- コラム
- セミナー
- キャンペーン情報
第15回 働き方改革による残業の変化はどうなる?企業・従業員視点から解説
第15回 働き方改革による残業の変化はどうなる?企業・従業員視点から解説

働き方改革を背景に、より働きやすい環境をつくるため、企業はさまざまな対応を迫られています。そのひとつが長時間労働の是正です。労働時間に関しては、従来から労働基準法によって規定されており、多くの企業では36協定を締結し、法律にのっとって労務管理が行われています。ただし、注意すべきは、働き方改革関連法によってその規定が変更されたということです。コンプライアンスを強化するためにも、企業としては従来から何が変更されたのかを正確に把握しておく必要があります。ここでは、法規制の変化を紹介しながら、残業時間に関してそれぞれの企業がどのように対応するべきかを解説します。
働き方改革とは?
働き方改革とは、働く人それぞれが自分に合った働き方ができるようにする取り組みです。政府が主導し、多様で柔軟な働き方を認めていく社会へと変容しようとしています。その一環として、2018年には「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」が公布されました。これは労働に関する8つの法律を改正するためにつくられた法律で、2019年4月から順次施行されています。
もともとこの働き方改革自体は、政府が2015年に掲げた「一億総活躍社会」の実現に向けた施策のひとつです。その背景にあるのは、少子高齢化という日本社会の大きな課題です。加速する少子高齢化に伴い労働力人口が減少すれば経済が縮小し、社会が維持できなくなってしまうという懸念がありました。
日本の人口の推移をみると、長期的に増加していた総人口は2000年代に入ると伸びが鈍化し、2010年は1億2,806万人となった。今後は、人口減少局面の中で、2030年には1億1,522万人、2050年には9,515万人になると見込まれている。
また、人口の年齢構成も大きく変化しており、生産年齢人口比率は1990年の69.5%をピークに低下し、2010年は63.7%となった。今後は、2030年に58.5%、2050年51.8%となることが見込まれている。高齢化率は長期的に上昇傾向で推移しており、2010年は23.1%となった。今後は、2030年に31.8%、2050年には39.6%となることが見込まれている。
このように、総人口が減少局面に入り、しかも少子高齢化が今後も進行していくなど、労働力供給が制約されるなかで、経済社会を支える労働力の確保は、ますます重要な課題となっている。
厚生労働省「平成23年版 労働経済の分析」より引用
そこで課題解決策のひとつとして考えられたのが、働き方改革です。多様で柔軟な働き方を推進し、長時間労働の是正を含め、働きやすい環境を整えることで、育児や介護で離職した人が再び働きやすくなったり、定年退職した人が働きやすくなったりと、日本社会全体の労働力を増やすという狙いがあります。
時間外労働とは?
時間外労働に近い言葉として、残業時間があります。どちらも決められた労働時間を超えて働いた際の、超過分の時間を指す言葉です。この残業時間については、2種類に分けることができます。
1つ目は「法定時間外残業」です。時間外労働と一般的に呼ばれているものはこちらで、1日8時間を超えた労働時間のことです。労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週間に40時間以内と決められています。企業は、これを超えて従業員に労働をさせた場合には、割増賃金を支払う必要があります。
2つ目は「法定時間内残業」です。所定時間外労働とも呼ばれており、各企業の就業規則で規定されている労働時間を超えた分の労働時間のことです。たとえば、所定労働時間が7時間と決められている企業で、8時間働いた場合に、この超過した1時間は法定時間内残業ということになります。また、法定時間内残業に対して割増賃金を払うかどうかについては、法律では規定がなく、各企業の規則によって異なります。
36協定(サブロク)の内容
上記のとおり、労働基準法で定められた法定労働時間は、原則1日8時間、1週間に40時間以内です。もし、法定労働時間を超えて、企業が従業員に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。 ただ、36協定を締結すれば、企業が従業員に対して無制限に時間外労働をさせられるわけではありません。同じ36条において、時間外労働は月45時間、年間360時間という上限が決められています。
また、職種や業種によっては繁忙期があり、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならないケースも考えられます。その場合には、あらかじめ「特別条項付き36協定」を締結しておくことで対応することが可能です。ただし、これはあくまで臨時的なものなので、限度時間を超えられるのは年6回までという上限があります。
働き方改革における残業規制の変化
ここまでに紹介してきた労働時間に関するルールについては、働き方改革関連法が施行される前から続いているものです。それが、法改正によってどう変わったのかを具体的に見てみましょう。
月の時間外労働の上限
働き方改革関連法によって労働基準法が改正され、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間と法律で定められました。実は、働き方改革関連法が施行される前から月の時間外労働の上限は決まっており、今回の法改正によって時間外労働の上限が変わったわけではありません。ただ、従来の上限はあくまで厚生労働大臣の告示によって示されたもので、法律で規定されたものではありませんでした。働き方改革によって法律で明確に上限を定めたことで、強制力が強くなったと言えるでしょう。また、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年に6回まで、という上限も法律によって定められました。
なお時間外労働の上限規制については、ただ労働時間を短くすることが目的ではないことに注意が必要です。企業としては、労働時間を短くしつつ、生産性を向上させるための取り組みが重要であることは認識しておくと良いでしょう。
特別な事情がある場合の上限
前述したとおり、働き方改革関連法が施行される前から、「特別条項付き36協定」を締結しておくことで、従業員に対して限度時間を超えて時間外労働をさせることは可能でした。また、その回数は年6回までとされていました。しかし、延長できる時間には上限が定められておらず、年6回までは無制限で残業することができてしまったため、大きな問題だったのです。そこで、この点についても法改正が行われました。たとえ「特別条項付き36協定」を締結していたとしても、「時間外労働は年720時間以内」とすること、「時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満」とすること、「時間外労働と休日労働の合計については、2~6カ月の月平均がすべて1カ月当たり80時間以内」とすることが、法律で定められました。
また、36協定届の様式は2021年4月1日から変更になっており、36協定届の一般条項は「様式第9号」、特別条項つきは「様式第9号の2」を使用するようになっていることに注意してください。
罰則規定
前二項の上限に関する規定が、法律で定められたことにより、罰則も追加されました。違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。従来であれば、違反をしたとしても行政指導が行われるものだったのに対して、かなり厳格化されたと言えます。また、この罰金刑については違反者(法定の上限を超えたしまった従業員)一人あたりの金額であることには注意が必要です。そして、企業としては、罰則を受けること以上に、法令違反による企業イメージの悪化という大きなダメージがあることを認識しておきましょう。
なお、この残業時間の上限についての法律の施行時期は、大企業においては2019年4月から、中小企業は2020年4月からとなっており、中小企業では対応に時間がかかることが想定されたため、猶予期間が設定されていました。しかし、現時点においてはすでに中小企業でも施行時期を過ぎています。まだ対応できていない場合には、法令遵守の観点から早急な対応が必要です。
働き方改革における企業がとるべき対策
厳格化された残業規制に対応するため、企業としてはまず社内に労働時間の上限について周知し、上限を超えないよう管理職を含めて全従業員に協力を求めることは大前提です。そのうえで、具体的に何をすれば良いのかについて、ここから対応策と注意点を紹介します。きちんと対策を行うことで、罰則を受けないようにするだけではなく、働きやすい環境をつくり、優秀な人材が集まる企業になることをめざしましょう。
従業員の労働時間の把握
まずやるべきことは、従業員一人ひとりの労働時間を正確に把握することです。誰がどれだけ残業をしているのか、部署もしくは人によって残業時間に偏りはないかなど、現状を知る必要があります。しかし、従業員が多い企業では、一人ひとりの状況を正確に把握するのが難しいこともあります。その場合には、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。出退勤時刻だけでなく、労働時間や残業時間など、必要な情報がシステム上で一元管理できるほか、残業時間が多くなっている従業員に対してアラート出す機能を備えたシステムもあり、勤怠管理業務の負担を軽減できます。
また、従業員が自主的に労働時間を短く申告したり、退勤後に上司に指示されて業務を行ったりする可能性もあります。そういったケースには、パソコンのログを利用した勤怠管理システムを活用し、改ざんを防止することが有効だと考えられます。
関連情報
残業時間の削減
労働時間や残業時間を把握できたからと言って、残業時間をすぐに削減できるわけではありません。まずは仕事量の調整を行いましょう。労働時間が長くなっている従業員ごとに、それぞれの仕事量が適切かどうかや、労働時間が長くなってしまっている原因を確認します。もし、仕事量が適切であるにもかかわらず、残業が発生してしまっている場合には、作業効率の見直しが必要です。また、一部の従業員に業務が偏ってしまっている場合には、部署内で仕事量を調整するようにします。それでも調整が難しい場合は、増員や業務効率化ツールの導入を検討するのも良いでしょう。
その他にも、多くの企業で実施されている対策としてノー残業デーの導入があります。実際に残業時間を削減するという役割のほか、従業員の労働時間に対する意識を高めることや、早く帰りやすい雰囲気をつくるという効果もあります。
関連情報
働き方改革により従業員が気を付けるべきこと
働き方改革により、自社内の労働環境が改善されることは、従業員にとって大きなメリットだと考えられます。しかし、実際には良いことだけではなく、従業員から不満の声があがったり、トラブルになったりするケースも発生しています。時間外労働の上限が法律で規定され、企業が対応を行うことによって、どのような影響が従業員にあるのでしょうか。注意すべきポイントを紹介します。
サービス残業の増加
法律で残業時間に上限が設けられたことで、企業としては残業を削減する必要があります。しかし、業務量の調整や増員、業務改善につながるツールの導入といった具体的な対策が講じられない可能性もあります。その場合、ただ残業時間の上限を遵守するよう指示されてしまい、勤怠管理システム上では退勤をしておいて、社内で残業をしたり、自宅に仕事を持ち帰ったりするなど、サービス残業が発生することが考えられます。
なお、サービス残業は、従業員本人が納得していれば良いという話ではありません。状況によりけりですが、サービス残業に対する賃金不払いがあるとして、企業が処罰を受ける可能性があります。また、自宅で仕事をするために重要なデータや資料を持ち帰った場合、情報漏洩などのセキュリティ上のリスクがあることは認識しておくべきでしょう。
収入の減少
企業が業務量の調整を適切に行ったうえで、残業時間を削減するように取り組んでいる場合、従業員としては労働環境が改善されるので、歓迎すべき状況と言えるでしょう。しかし、実際には残業をすることで生活費をまかなっている従業員も少なくありません。割増賃金として支払われる残業代は、収入を増やすという意味では大きなメリットなのです。そういった従業員にとって、残業時間の削減は大幅な収入減につながってしまうというデメリットがあるのです。
この問題への対応策として、所属する企業が副業を認めてくれる場合には、副業を検討してみましょう。働き方改革によって以前よりも時間に余裕ができている場合、時間の有効活用という意味でも、副業はおすすめです。
まとめ
企業としては、法律で定められた時間外労働の上限を遵守するためには、制度の見直しだけではなく、社内の意識を変えていく必要があります。目的をきちんと共有したうえで、協力を呼びかけましょう。また、ルールが守られているか否かだけに目を向けるのではなく、従業員に負担がかかっていないかも把握することが重要です。特に残業代がなくなり、収入が減ってしまっている場合には、仕事に対するモチベーションが下がってしまう可能性もあるため、それにより生産性が低下しないよう注意しましょう。