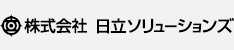5分でわかる
セキュリティコラム
パスキーとは?
注目のパスワードレス認証「パスキー」
導入ガイド

さまざまなオンラインサービスを利用する際に、主な認証方法として使われている「パスワード認証」には、セキュリティ面で多くの課題が存在します。本記事では、パスワード認証の問題点を洗い出し、注目されている認証方法「パスキー」について、その概要や利点、課題を解説します。また、安定したパスキー運用を実現するための準備や実施項目についても詳しく説明します。
1. 「パスワード認証」の課題と「パスキー」とは
「パスワード認証」は、現代のデジタル社会において一般的な認証方法として使われている一方で、セキュリティや使い勝手の面で課題があります。この章では、パスワード認証の課題とパスキーの概要や特長を説明します。
パスワード認証の課題
2つの課題を紹介します。
セキュリティリスク
第三者によるパスワードの推測や、ブルートフォース攻撃※1などからのパスワード流出により、情報漏洩をはじめとするさまざまなセキュリティ事故に直結するリスクが常に存在します。
ユーザビリティ
多くのパスワードを覚えるのは困難で、忘れてしまった場合にはリセット手続きが必要となるため、ユーザーにとって大きな負担となっています。
上記の課題を解決するとされるのが、「パスキー」という認証方法です。
※1 ブルートフォース攻撃:暗号解読(パスワードや暗号鍵の解読)のための総当たり的な攻撃。
「パスキー」とは?
指紋認証や顔認証に代表される生体情報やスマートフォンなどのデバイス自体を鍵として認証に使用するのがパスキーです。FIDO(ファイド)アライアンス※2が策定したこの技術は、Web技術の標準化団体であるW3C(World Wide Web Consortium)も協力して開発しました。パスキーを活用することで、ユーザーは煩わしいパスワードの入力をすることなく、より安全かつスムーズにオンラインサービスを使うことができます。また、企業側もパスワード関連のセキュリティインシデントの発生リスクを低減できるというメリットがあります。
※2 FIDOアライアンス:FIDOは、Fast Identity Onlineの略。FIDOアライアンスは、指紋認証や顔認証をはじめとする生体認証をベースに安心安全で使いやすい認証基盤の構築をめざす業界団体。
パスキーの特長
パスワード認証の問題を解決し、より安全で便利な認証方法を提供するパスキーの特長について、技術的な背景を交えて説明します。
高いセキュリティ
パスキーは生体情報やデバイス固有の情報の利用によって、パスワードのように盗まれたり、推測されたりするリスクが非常に低く、ブルートフォース攻撃にも有効です。
優れたユーザビリティ
生体やデバイスの情報を用いた認証でアクセスできるため、ユーザーが数多くのパスワードを設定したり、覚えたりする必要はなく、またパスワードを忘れて再設定する手間も発生しません。
多様なデバイス対応
パスキーは複数のデバイスと同期できるため、一度アカウントに登録した鍵情報を使って、異なるデバイス(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)からログインが可能です。
2. パスキーの仕組み
この章では、パスワードとパスキーを認証方法、安全性、使い勝手の観点から比較します。また、パスキー認証の仕組みも確認します。
パスワードとの違い
文字や数字、記号などをランダムに組み合わせ、自分だけが知っている文字列にして自分自身であることを確認するための鍵として用いるのが、パスワード認証です。一方、生体情報やデバイス自体を鍵として使用するのがパスキーです。認証方法のほかに、安全性や使い勝手にも以下のような違いがあります。
| パスワード | パスキー | |
|---|---|---|
| 認証方法 | ユーザーが設定した文字列 | 生体情報やデバイスの情報 |
| 安全性 | 推測されやすい文字列の設定や同じ文字列の使い回しにより情報漏洩リスクが高まる | 生体情報やデバイス固有の情報を利用するため情報漏洩リスクが低い |
| 使い勝手 | 覚えにくい 入力の手間がかかる |
生体情報やデバイス情報を読み込ませるだけで容易に利用できる |
公開鍵暗号にもとづく認証
パスキーは、FIDO2※3の一部として導入された技術です。FIDO2の主要な認証規格であるWebAuthn※4やCTAP※5をもとにしており、シームレスかつ安全なログインを実現します。具体的には、公開鍵暗号方式を使用してユーザーの認証情報を保護する仕組みです。その一連の流れを鍵と鍵穴に例えて解説します。
※3 FIDO2:2018年に公開されたFIDOの最新バージョン。
※4 WebAuthn:パスワードに依存しない認証を実現するための「FIDO2」という認証技術を構成する技術の一つ。
※5 CTAP:Client to Authenticator Protocolの略。WebAuthnと連携して動作し、ユーザーのデバイスと認証機器の間の通信を管理する。
- 鍵ペアを生成
サービス登録時、ユーザーは公開鍵と秘密鍵のペアを生成します。公開鍵はサービス側に保存されます。
公開鍵:サービスに初回登録する際に公開され、サービス側に保管される鍵で、“鍵穴”のような役割を果たします。
秘密鍵:デバイス内に安全に保管されるユーザー本人専用の鍵で、“鍵本体”のような役割を果たします。 - ログイン認証プロセス
・ログインするときに、サービス側がユーザーに認証を要求します
・デバイス側で秘密鍵を用いて「デジタル署名」を生成します
・この「デジタル署名」をサービス側に送信し、サービス側で保管されている公開鍵を用いて検証します
・検証が成功すると、本人であることが認証されてログインが許可されます
国際標準規格「FIDO」とパスキー
パスキーはFIDOアライアンスによって策定された認証規格で、各システムのユーザーアカウントに紐づけられた、暗号化されたFIDOの資格情報のことです。
3. パスキーのメリット
パスキーは、これまでスタンダードであったパスワード認証が抱えるセキュリティの課題とユーザビリティの低さを克服します。この章は、技術的な要素を交えたパスキーのメリットを説明します。
メリット1. 強固なセキュリティ
耐タンパー性
生体情報やデバイス固有の情報は漏洩しにくいため、物理的な攻撃に対しても高い耐性を示します。
非複製性
生体情報やデバイス固有の情報は複製が至難であり、なりすましのリスクを低減します。
エンドツーエンドの暗号化
公開鍵暗号を用いてエンドツーエンドで暗号化するパスキーは、通信中の情報が漏洩するリスクを最小限に抑えます。
フィッシング攻撃への耐性
パスキーは、ドメインに紐づいて公開鍵が生成され、同じドメインのときにのみ認証情報が送信されます。そのため、たとえフィッシングサイトに誘導されたとしても、初回登録時と異なるドメインでは認証されることはありません。
メリット2. 優れたユーザビリティ
スムーズな認証
生体認証やデバイス認証を用いることで、ユーザーは手間なく迅速にサービスにアクセスできます。
クロスデバイス認証
デバイス間でパスキーを同期させることで、複数のデバイスからサービスを利用することが可能です。サービスの認証要求はスマートフォンで行い、サービスの利用はPCで行うといったデバイスを跨いだ認証ができます。
パスワード管理の負荷軽減
複数のパスワードを設定したり覚えたり、忘れた際に再設定するなど、ユーザーのパスワード利用負担を大幅に軽減します。
4. パスキー導入における課題と成功のポイント
セキュリティの高さや利便性の良さから注目されているパスキーですが、導入にはいくつかの課題があります。この章では、パスキー導入時の課題や知っておきたいリスク、そして導入を成功させるために考慮すべき4つのポイントを解説します。
デバイス面の課題とセキュリティリスク
互換性の課題
パスキーは、iOS、Android、Windowsなど各プラットフォームのIDに紐付けて作成されるため、プラットフォームが異なる場合は同じパスキーを使用することができず、シームレスな同期が課題となっています。
デバイスの盗難・紛失
パスキーは、デバイス内に秘密鍵が保管されるため、デバイスを跨いだ認証など利便性がよい一方で、デバイスの盗難・紛失時には、認証情報の漏洩に直結するリスクを伴います。
緊急時の認証手段
システム障害や災害時、デバイス紛失時など、パスキーによる認証が困難となる場合の代替策を検討しておく必要があります。また、パスキーの再登録を行う場合には、適切な手順を踏まなければセキュリティホールとなり悪用される可能性が生じるなどのリスクがあることを認識しておきましょう。具体的な代替手段については後述します。
ユーザー教育と導入コストの課題
ユーザー教育の必要性
パスワードレス認証という新たな認証方法への移行には、ユーザーへの十分な教育が不可欠です。特に、ITに不慣れなユーザー層への周知徹底には、時間と労力がかかります。
既存システムのパスキー認証への対応
パスキーに対応していない既存システムがある場合、改修が必要となります。システムの規模や改修ボリュームによっては、導入コストの増大や運用開始までの期間が長引いてしまうことも考えられます。また、既存システムがパスキー認証に対応するまでの間は、従来の認証方法と併用する形となり、ユーザーにとって負担となります。
パスキーの導入を成功させるために考慮したい5つのこと
次に、パスキー導入を成功させるために考慮したい5つについてです。
- 段階的な導入とパイロットプロジェクト
全社導入の前に、まず一部の部門やサービスで試験的に導入し、その結果を踏まえて段階的に拡大することが推奨されます。 - ユーザーサポート体制の構築
ユーザーからの問い合わせに対応できるヘルプデスクを設置し、スムーズな移行を支援する体制を用意しておく必要があります。 - セキュリティ意識の啓発と教育
ユーザーのセキュリティ意識の向上を目的としたセキュリティ教育を実施し、情報漏洩のリスクを低減します。特に、デバイス紛失時のリスクについて事前に周知徹底し、紛失を防ぐ対策や万が一紛失した場合の対応などの教育を行うことが望ましいです。 - リスクアセスメントの実施
導入前にリスクアセスメントを行い、潜在的なリスクを特定し、パスキー導入に支障がないよう対策を検討・実施しておくと安心です。 - 認証基盤製品を活用した移行
技術的な面で、従来のパスワード認証からパスキー認証へのスムーズな移行や段階的な移行のために、幅広いデバイスや認証方法に対応している認証基盤製品の活用を検討することもひとつです。
5. パスキー導入前の準備と注意点
この章では、導入前に必要な準備や導入時の注意点を解説します。
パスキー導入前に必要な準備
導入前に必要な準備として5点紹介します。
- 対応デバイスの整備
デバイスの互換性:パスキーを使うデバイスがパスキー認証をサポートしているか確認します。スマートフォンやPCの多くはすでに対応していますが、古いデバイスでは対応していない場合があります。
ブラウザーの対応:使用Webブラウザーがパスキー認証をサポートしているか確認します。主要なブラウザー( Google Chrome 、 Firefox 、 Safari 、 Microsoft Edge など)は、おおむね対応しています。
サービス側の対応:利用するオンラインサービスやアプリケーションにおける、パスキー認証の対応可否を確認します。すべてのサービスがパスキーをサポートしているわけではないため、事前の確認が必要です。 - 段階的な実装
一部のサービスから段階的に実装する計画を策定します。段階的にすることで、新たな認証方式への問い合わせが発生した場合にも余裕をもって対応することができます。また、各ユーザーのリテラシーを考慮し、いきなりパスキー認証に切り替えるのではなく、パスワード認証とパスキー認証のどちらかをユーザーが選べるようにしたり、二要素認証として組み合わせたりする方法を検討します。そうすることで、リテラシーの高いユーザーはパスキーを選択するなど、徐々にパスキーへの移行を推進できます。
パスキーに抵抗があるユーザーに対しては、パスワードマネージャーの利用を案内することも一つです。パスワードマネージャーは、ユーザーが認証に用いたパスワードを保存し、ドメインにもとづいて次回以降は自動入力で認証ができます。これまで“ユーザー自身の記憶により管理”していた認証手段を、“システム側で管理”します。ユーザーが自分でパスワードを入力せずに認証できる方式はパスキーに似ているため、パスワードマネージャーを利用することで、パスキーに慣れていないユーザーにも理解を促し、パスキーの利用を段階的に進めます。 - ユーザー教育
ユーザーがパスキーについて、またパスキーの設定や使用方法を理解できるように、パスキーのメリット、設定方法、トラブルシューティングを含めた教育プログラムを用意します。特に、パスキーに馴染みのないユーザーには具体的な説明が役立ちます。マニュアル、動画、ハンズオン研修など、多様な教育方法を組み合わせることで、ユーザーの理解度を向上させます。 - 経営層のコミットメント
パスキー導入には、組織全体で協力体制を築くことが重要なため、経営層のコミットメントが不可欠です。経営層の理解を得ることで、パスキー導入に係る予算や人材の確保がスムーズに進みやすくなります。 - 専門家の活用
導入には技術的な課題やリスクが伴うため、技術的な知見が豊富な専門家を活用することで、パスキー導入に係る不安や課題を解決でき、スムーズな導入を推進します。また、技術的なアドバイスだけでなく、ユーザー教育の実施も依頼することで導入担当者の負荷を軽減します。
導入時の注意点
続いて、導入時に注意しておきたい点は以下のとおりです。
運用管理
パスキー特有の注意点ではありませんが、実運用においては、通常時だけでなくインシデント発生時についても考慮する必要があります。
通常時は認証ログを詳細に記録・分析することで、不正アクセスやセキュリティインシデントを早期に検知。問題が起きた際の原因究明や対策に役立てます。また、インシデントへの備えとしては、パスキーに関するインシデントが発生した場合の対応手順を明確化し、対応体制を整えておくことで、被害を最小限に抑えます。
代替手段の確立
デバイスの故障や紛失など、何らかの理由によりデバイスに保存されているパスキーを利用できなくなった場合に備えておくことも重要です。たとえば、事前に別のデバイスにパスキーを登録しておくことや、パスキーを同期するクラウドサービスを利用する方法があります。そうすることで、デバイス内のパスキーが使えなくなった場合でも、別のデバイスのパスキーを利用したり、新たなデバイスにパスキーを再設定したりすることができます。また、利用するシステムへの認証方法として、パスキー以外(例:パスワード+ワンタイムパスワードなど)も使えるように設定しておくことも手段の一つでしょう。
このような注意点を確認しておくことで、事前に対策を講じることができ、スムーズなパスキーの運用を推進します。
6. 安定したパスキー運用のための実施項目2つと適用例
安定したパスキーの運用を継続的に行うために、2つの実施項目を解説します。
- セキュリティとサポート
デバイスに依存するパスキーは、デバイス自体のセキュリティを強化することが必要です。例えば、OSやアプリケーションの定期的なアップデートを行い、最新のセキュリティパッチを適用します。紛失・盗難対策として遠隔ロック機能などを活用する方法もあります。また、運用していく中で問題が発生した際に迅速に対応できるサポートチームを設けることも重要です。 - 定期的な評価と改善
パスキーの運用状況を定期的に評価し、現状や問題点を把握することも、安定したパスキー運用のために必要です。指標としては、認証成功率、エラー発生率、ユーザーからの問い合わせ件数・内容などを参考にします。管理者側で運用状況や問題点を認識することで改善策を検討することや、ユーザーからの問い合わせを活用したFAQを作成して不慣れなユーザーに配慮することで、安定したパスキーの運用につなげます。
パスキーの適用例
つづいて、適用例とその効果についてです。
- 適用例①:金融機関
ネットバンキングサービスのログイン認証にパスキーを導入。これにより、指紋認証や顔認証などの生体情報を用いたログインが可能となり、フィッシング攻撃などの被害が大幅に減少。高いセキュリティ水準を実現したことで、顧客からの信頼を獲得。 - 適用例②:IT企業
社内システムにパスキーを導入。特定のデバイスからの認証のみ許可することでアクセスを制御し、強固なセキュリティを実現。また、ユーザビリティの面でもユーザー個人によるパスワード管理の負荷軽減により、従業員の生産性が向上。 - 適用例③:Eコマースサイト
顧客向けのログイン認証にパスキーを採用。ユーザーによるネットショッピングやオンラインサービスのスムーズな利用を実現。顧客満足度向上に加え、パスワード流出によるなりすましを防止しセキュリティが向上。
7. まとめ:パスキー導入による、より安全なデジタル社会の実現
セキュリティの向上と優れたユーザビリティを評価して多くの企業がパスキーの導入を積極的に進めており、主要なブラウザーやOSもパスキーに対応し始めています。今後、より多くのデバイスやサービスがパスキーに対応することで、パスワードレス認証が主流となることが期待されます。パスワードからパスキーへの移行は、より安全で便利なデジタル社会を実現する第一歩です。この新たな技術を積極的に活用し、誰もが安全で安心できるデジタル活用を推進してみませんか。
※本ページの一部は、生成AIにより生成されたコンテンツを使用しています。
この記事に関連するおすすめ製品
IceWall MFA
アプリケーションやクラウドサービスを改修せずに、多要素認証による認証強化を実現します。また、Webシングルサインオン(SSO)の機能も有しているため、認証強化とSSOを同時に実現します。