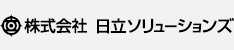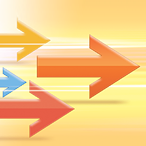システムの内製化を成功させるには
~内製化の重要性やメリット・デメリットも解説
近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に伴い、企業による「システム開発の内製化」が注目を集めています。従来、日本企業の多くはシステム開発をベンダーに委託してきましたが、ビジネス環境の急速な変化に対応するため、自社内でシステム開発や運用を行う動きが加速しています。
特に、クラウドを活用したシステム連携の内製化は、企業の俊敏性や競争力に大きな影響を与える要素となっています。しかし、内製化には多くの利点がある一方で、課題も少なくありません。そのため、各企業の状況に応じた戦略的なアプローチが求められます。
本記事では、システム内製化についての基本知識、その背景、導入する意義、メリット・デメリットなどに焦点を当てて解説していきます。さらに、内製化を成功に導くための具体的なポイントや、ノーコード/ローコードツールの選定方法まで、実践的なアドバイスも提供します。
目次
システム内製化とは

システム内製化とは、企業が従来外部に委託していたシステム関連の業務を、自社内で対応する体制へと切り替えることを指します。具体的には、システムの設計、開発、保守、運用、さらには継続的なアップデートを自社の人材や設備を活用して行うことが含まれます。
システムを内製化することで、企業は自社の特有のニーズや業務プロセスに適したシステムを構築することができます。これにより、外部ベンダーに頼ることなく迅速かつ柔軟な対応が可能になるだけでなく、技術的な知識が社内に蓄積されることで、企業の競争力が長期的に強化されます。
さらに、セキュリティおよびコンプライアンスの観点からも、社内での管理体制を強化することにも役立ちます。たとえば、データの取り扱いやアクセス権限の管理を外部に委託する場合など、情報漏洩や不正アクセスの面でのリスクも回避することができます。
外注(アウトソーシング)との違い
システム開発における外注(アウトソーシング)と内製化の最も大きな違いは、業務の実施主体にあります。外注では、システムの開発や運用を専門の IT 企業やベンダーに委託します。そのため、自社にIT人材がいなくても専門知識や最新技術を持つ外部リソースを活用できます。また、自社で抱える必要のある IT 人材をできる限り抑えられるというメリットがあります。
一方、内製化では自社の人材や設備を使用するため、より自社のビジネスニーズに即したシステム開発が可能となり、作業スピードの向上が見込めます。
内製化が注目される背景
システム内製化が注目される背景には、大きく3つの要因があります。
1つ目は、社会の変化やビジネスニーズに迅速に対応する必要性が挙げられます。コロナ渦の影響により、ニューノーマルな社会活動への対応が求められる中、DXを推進する動きが加速しています。また、DXを推進する背景として、経済産業省のレポート*1にある「2025年の崖」の影響もあります。「2025年の崖」とは、DXを推進しないことによって競争力が低下すると、2025年から年間約12兆円もの経済損失が発生するという予測のことです。DXを成功させるためには社会の変化に迅速に対応し、データを効果的に活用することが不可欠となりますが、このスピードに対応するには時間のかかる外注よりも内製化が適しているといえます。
2つ目はIT人材の不足と開発コストの上昇が挙げられます。日本では少子高齢化にともなう労働者人口の減少を受け、慢性的にIT人材が不足しています。経済産業省の試算によれば、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されており、拡大するDXの需要に対しても人材の供給が追いついていません。さらに、物価の上昇により開発コストも増加しており、企業にとってはこの二重の負担が大きな課題となっています。
こうした状況下で外注に頼り続けることは、コスト面でのリスクが高まるだけでなく、必要なシステム開発が適時に行えない可能性も出てきます。そのため、自社でIT人材を確保・育成して内製化を進めることで、長期的なコスト削減と安定的なシステム開発体制の構築をめざす企業が増えています。
最後の理由として、開発ツールの発展があります。プログラミングの専門知識がなくてもある程度の機能を持つアプリケーションや、システムを開発できるノーコード/ローコード開発ツールが登場しました。
さらに、AI技術の発展により、コード生成や自動テストなどの開発支援ツールも発展しています。これらのツールを活用することで、専門性の高いエンジニアでなくても、ある程度の品質を保ちながらシステム開発を行うことができます。
システム内製化のメリット
次はシステム内製化を行うメリットを解説します。
変化への対応力
システム内製化を行うと、法改正や市場の変化に合わせて柔軟にシステムを改修することができます。ベンダーに依頼した場合は、改修の要件定義やすり合わせなどの時間が発生してしまうため、状況の変化に対応するころには次の変化に対応しなくてはならないケースさえあります。
近年では、インボイス制度やテレワークの導入といった、迅速な対応が求められる課題が増えています。これらは、法改正や社会的なニーズの変化に応じてスピーディーに対策を講じる必要がある代表的な事例です。これに遅れが生じると、業務の停滞やコンプライアンスリスクの増大につながり、企業の競争力に大きな影響を及ぼすため、即応力が重要になります。
開発スピードの向上
内製化を行うと、社内で意見交換や意思決定が完結するため、コミュニケーションコストが低減します。たとえば、新機能の追加や既存機能の改修が必要になった場合、外部委託では契約変更や見積もりの取得などのプロセスが必要ですが、内製化環境では即座に着手することができます。
コストの適正化
内製化を進めることで、外部ベンダーへの委託していたコストを大幅に削減することが可能になります。とはいえ、内製化の初期段階では、人材採用や育成、インフラ整備などの投資が必要になるため、短期的にはコストが増加する可能性があります。しかし、中長期的な視点で見れば、これらの初期投資は将来的なコスト削減に繋がります。
また、必要な機能に絞った開発ができるようになります。外部に委託する場合、すぐには必要ではない機能も含めた開発になる場合がありますが、内製化では必要な機能のみを開発することで、無駄なコストを削減できます。
知見・ノウハウの蓄積
外部委託でシステム開発を行うと、開発時のノウハウや知見はベンダーに蓄積します。内製化では、ノウハウや知見は自社内に蓄積されていきます。そのため、自社のIT人材のスキルや管理能力、トラブルシューティング力などの組織の競争力が向上していきます。
また、システムがどのように動作しているのかわからない、いわゆる「ブラックボックス化」を防ぐことができます。そのため、社内でシステム全体の構造やセキュリティリスクの把握が容易になります。
人材の育成
内製化にともない、IT人材の育成も進みます。プロジェクトを通してツールを学ぶ機会が増えることで、要件定義から設計、開発、テスト、運用まで、システム開発の全工程に渡る経験を得ることができます。
また、IT部門の社員が直接ビジネス部門とやりとりする機会が増えるため、ITだけでなくビジネスにも精通した人材が増えていきます。具体的には、ビジネス目標達成のために適したソリューションを提案できる能力や、技術者と非技術者の橋渡しができる能力などが養われます。
これらの経験を通して社員は顧客や自社に対して自身が貢献していることを実感しやすくなるため、モチベーションやパフォーマンス、人材定着率の向上など、さまざまなメリットが期待できます。
システム内製化のデメリット
一方で内製化を進める際のデメリットも存在します。
初期投資と運用コストの増加
まず、システムを運用するための初期費用やランニングコストがかかります。たとえば、オンプレミス環境で運用する場合、自社サーバーを使用するためのハードウェア購入費が必要です。さらに、OSや各種ソフトウェアの使用にともないライセンス費用も発生します。
また、ランニングコストとしては、人件費やセキュリティ対策費、クラウドサービスの利用料などが挙げられます。
継続的なライセンス料がかかるものの、オンプレミスからクラウドへ移行することで、サーバー購入費などの初期費用、セキュリティ対策費や運用コストは大幅に下げることができます。そのためトータルで考えるとクラウドに移行したほうがトータルの費用を抑えることができる場合が多くあります。
IT人材の確保・育成の課題
内製化にはシステム開発できる人材が不可欠です。人材の確保には、採用や教育が必要になります。そのため、ポータルサイトやスカウトサービスなどを活用した際の採用コスト、プログラミングスキルを身につけるための教育コストなどが発生します。
しかしながら、専門性の高いIT人材の採用は難しい状況にあります。IT人材は不足しており、より給与水準の高い企業との取り合いになってしまいます。
また、社内で既存の人材をIT人材に育て上げようとする場合には、プログラミングやシステム設計などのスキルを身につけるために時間がかかります。少なくとも1年ほどは必要になり、実践的なレベルに達するにはさらに長い期間が必要になるでしょう。
ノーコード/ローコードツールを取り入れると、事業部門の非IT人材でも開発できるようになり、IT人材不足の問題が解決する可能性があります。
システム内製化を成功させるポイント
次にシステム内製化を成功させるためのポイントについて解説します。
段階的な内製化の推進
システム内製化を行う際のよくある失敗として、一気にすべてを内製化してしまうことが挙げられます。
まずは比較的リスクの低い、かつ成果の見えやすい小規模なプロジェクトを選択することが推奨されます。たとえば、特定の部門内での業務効率化や、限定的なシステム間連携などが適しています。小さな成功によって内製化のプロセスや課題を把握し、組織内でのノウハウを蓄積していくとよいでしょう。
ノーコード/ローコード開発ツールの導入
システムの内製化を成功させるためには、ノーコードやローコードツールの活用が非常に効果的です。ノーコード/ローコードツールを活用することで、専門的なプログラミングスキルがなくても、業務部門のスタッフが直接システム開発に携わることが可能になります。
ノーコード/ローコードツールは、見やすくわかりやすい画面操作を通じて直感的にシステムを構築できるため、従来のプログラミング手法と比べて開発時間を大幅に短縮することができます。また、プリセットされたテンプレートや機能を活用することで、複雑な処理も比較的容易に実装できるようになります。
推進体制を整える

システム内製化を成功させるためには、適切な推進体制を整えることが不可欠です。よくある失敗例は、DX推進チームが業務部門と対立している、DX推進チームが社内ITベンダーのような扱いになってしまうパターンです。
それに対し、理想的な体制は、IT部門、業務部門、経営企画などの部門を越えたメンバーで構成されるフュージョンチームの形です。IT部門はシステムの技術的側面を、業務部門は実際の業務プロセスと課題を、そして経営企画は全社的な戦略の面で意見を出し合います。会社としてのDXの目的と目標を明確に共有し、チームメンバー全員がそれを自分ごととして捉える意識を醸成することが重要です。
伴走型支援の活用
いきなりシステム内製化を進めようとしても、技術力不足や管理・進行の不慣れなどが原因でうまくいかないことがあります。その場合には、ベンダーの伴走支援を活用する方法があります。
伴走型支援には主に2つの形態があります。1つ目は、フュージョンチーム型の支援です。この方式では、ITベンダーの専門家が社内のフュージョンチームに参加し、技術伝承と作業分担を行います。ベンダーのメンバーは自社のチームメンバーと密接に協働し、プロジェクトの進行に合わせて必要なスキルや知識を共有します。
たとえば、システム連携の複雑な部分や高度な技術を要する箇所は、初期段階ではベンダーが担当し、社内メンバーはその過程を学習します。その後、徐々に社内メンバーが主導権を取り、最終的には自立して開発や運用ができるようになることをめざします。
2つ目は、サポート型の支援です。この形態では、ITベンダーは直接的な開発作業には携わらず、アドバイスをする立場で支援します。これには技術選定の支援、開発方針の策定、ベストプラクティスの共有、トラブルシューティングなどが含まれ、社内チームの自主性を尊重しつつ、必要な時に専門的な知識やアドバイスを得られるというメリットがあります。
内製化をすすめるためのノーコード/ローコードツール選定のポイント

ここではシステム内製化をするためのノーコード/ローコードツールを選定する際の流れとポイントを解説します。ポイントはいくつかありますが、ここでは主な4つをご紹介するにとどめ、その他についてはまた別の記事で詳しく解説します。
製品選定の流れ
内製化を進めるためのノーコード/ローコードツールを選定する際の一般的な流れは、以下のようになります。
- 製品調査
- 比較・検討
- PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施
まず、製品調査の段階では、市場に存在するさまざまなノーコード/ローコードツールについて情報を収集します。この過程では、各製品の機能、特徴、価格帯、対応しているプラットフォームなどの基本情報を幅広く集めます。
次の比較・検討の段階では、収集した情報をもとに自社のニーズや要件に照らし合わせて各製品を評価します。机上での調査だけでなく、可能であれば製品のデモンストレーションを受けることや、試用版を利用することで、実際の使用感を確認することが有効です。
最後に、PoCの実施に進みます。PoCとは、実現可能性や実際の効果などの検証プロセスのことを指します。この段階で、製品の機能や使いやすさだけでなく、既存のシステムとの統合性や社内のIT環境との親和性なども確認します。
ポイント1:目的に合っているか
自社で解決したい具体的な課題や、利用シーンに適した製品かどうかを確認します。たとえば、ウェブアプリやモバイルアプリの開発、あるいは業務プロセスの自動化など、目的に応じて適切なツールは異なります。そのため、検討しているツールのユースケースや事例集を収集し、実際に自社の目標を達成できるかどうかを確認することが重要です。
ポイント2:コスト
ノーコード/ローコードツールの選定におけるコスト評価は、単純なライセンス費用の比較ではなく、総所有コスト(TCO)の観点から行うことが重要です。TCOには、初期投資、運用・保守費用、インフラ費用、人材育成コスト、サポート体制などが含まれます。
ここで注意すべきことは、製品によって課金体系が大きく異なる点です。ユーザー数、データ処理量、機能ごとの課金など、さまざまなモデルがあるため、自社の利用形態に適切な選択をすることでコスト削減につながります。
また、内製化による開発コストの抑制効果も考慮するとよいでしょう。外部委託と比較して、開発期間や委託費用がどの程度削減されるのかを確認します。
ポイント3:サポート体制
ノーコード/ローコードツールを選定する際は、サポート体制の手厚さが重要になります。適切なサポートがあれば、内製化の過程で直面する課題を効果的に解決でき、円滑な導入と運用が可能になります。特に確認すべき点は、サポート時間、販売代理店のサポート品質、対応言語などです。
たとえば、24時間365日対応と平日の特定時間帯のみの対応では、緊急時の対処に大きな差が出ます。販売代理店のサポート品質も重要で、スキルレベルや対応の迅速さが製品の使いやすさに直結します。特に、日本語に対応していない海外製品の場合は、国内の販売代理店の一次サポート対応が重要になります。
ポイント4:開発のしやすさ
ノーコード/ローコードツールの選定で特に重要なのはプログラミングスキルのない人材でも開発がしやすいかどうかです。
開発しやすいツールは、開発効率を大幅に向上させ、内製化の成功に直結します。開発のしやすさを評価する際は、ローコード/ノーコード機能の比較、デバッグやテスト機能の確認、そして使用者に応じた適切なツールの選択が重要です。
ローコード/ノーコード機能の比較では、視覚的な開発環境の使いやすさ、提供されるテンプレートや部品の豊富さ、カスタマイズの柔軟性などを評価します。デバッグやテスト機能については、エラーの検出しやすさ、ログの確認のしやすさ、テストデータの作成や管理の容易さなどを確認します。実際に業務に関わる方に使ってもらうとより適切な評価ができるでしょう。
基幹系システムの連携を行うIT部門向けのツールと、部門業務の自動化を行う現場部門向けのツールでは、求められる機能や使いやすさが異なります。IT部門向けのツールではより高度な制御や拡張性が求められる一方、現場部門向けのツールではより直感的な操作性が重要になります。
したがって、開発のしやすさを十分に考慮し、使用者のスキルレベルや開発対象に適したツールを選択することで、効率的な内製化と持続可能な開発体制を構築することができます。
システム間連携を内製化できるiPaaS製品
内製化の対象は業務アプリケーションやモバイルアプリなどさまざまです。近年はクラウドシフトに伴うSaaSやオンプレ間のシステム連携や業務プロセスの自動化のニーズが多く、その内製化が注目されています。
システム間の連携を内製化したいと考えている方にお勧めなのが、iPaaS(Integration Platform as a Service)です。iPaaSは、複数の業務システムを統合するためのクラウドベースのサービスであり、クラウドやオンプレミスのシステム間でのデータ連携・共有を実現します。
日立ソリューションズでは、定評あるiPaaS製品の1つである「Workato(ワーカート)」を提供しています。Workatoはクラウドサービスやオンプレミスシステムを含むさまざまなアプリケーションを、ワンプラットフォームで効果的に連携し、業務プロセスを自動化することが可能なツールです。
TeamsやSlackと連携するチャットボット機能に加え、ローコード/ノーコード開発環境を活用することで、IT部門だけでなく、業務部門のスタッフも直感的に操作できる仕組みが整っています。
Workatoの導入事例:低コスト・短期間で建設DXの推進を加速。レガシーシステムデータのリアルタイム活用をAPI連携で実現
まとめ
内製化には変化への迅速な対応、開発スピードの向上、コストの適正化、組織内の知見とノウハウの蓄積といった多くのメリットがあります。一方で、人材の確保や育成、初期投資などを踏まえ、状況にあわせてどこまで内製化すべきかを見定める必要があります。
内製化を成功させるポイントは、段階的な内製化の推進、ノーコード/ローコード開発ツールの効果的な活用、適切な推進体制の整備、そして必要に応じた外部の伴走型支援の活用にあります。特に、ノーコード/ローコードツールの選定においては機能や使いやすさだけでなく、コスト、サポート体制、開発のしやすさなど、多角的な視点から評価する必要があります。
また、内製化を進める際にはシステム連携に適したツール選定が重要になります。特に複数のシステムがある企業では、それらを効果的に連携させることで情報の一元管理や業務の自動化が可能になります。iPaaS製品を活用すれば、クラウドやオンプレミス間のデータ連携や共有がスムーズに行えます。
日立ソリューションズではWorkatoのご提供および伴走支援を行っています。さらに、豊富な自社利用実績をもとに充実したサポートも行っています。システム間連携や業務プロセスの自動化の内製化をお考えの方は、お気軽にご相談ください。